霜寒の候の意味は?時期?使い方は?
読了までの目安時間:約
5分

「霜寒(そうかん)の候」といえば
11月に使われるこの時候の挨拶ですが
意味を知らずになんとなく
使っていたりしませんか?
そこで今日は「霜寒の候」の意味や
使える時期、
また、11月に使えるその他の
時候の挨拶について簡単にまとめて
みました。
意味を知ってから使うと、
また味わいも格別ですよ!
霜寒の候の意味は?

紅葉も色づきだし、肌寒さを感じだすと
少しずつ冬支度の気配も
近づき始めてきたのが実感できますね。
そんな秋の終わり、冬の気配を
感じ始めたころに使うのが、
「霜寒の候」
です。
意味は、霜が降るほど寒さが増してきた
ということで、
季節が秋から冬に移り変わる様を
一言で表したとてもきれいな言葉なんです。
日本では先人の方々が、
豊かな四季の訪れを折々の言葉に変え、
慕う相手へ尊び敬う気持ちを表し伝える
奥ゆかしくも美しい文学的教養の
1つとして
季語を残してくれました。
遠くの相手への敬意の表し方を
手紙という形で届ける際に、
慣用句に季節の色を添えて贈るのが
「時候」の挨拶。
そう思うと、
「ちょっと面倒・・・・」
な時候の挨拶も、素敵な習慣に
思えてきますよね^^
霜寒の候が使える時期は?
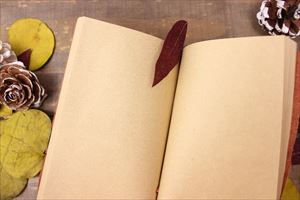
さて、この「霜寒の候」が使える時期ですが
基本的には11月いっぱい使える時候の挨拶です。
時候の挨拶には、「立冬の候」のように
二十四節気に基づいたものと
「霜寒の候」のように季節の様子を
表したものがあります。
二十四節気に基づいたものですと、
次の節目までしか使えませんので
使う時期はある程度決まっています。
例えば、「立冬の候」は
立冬(11月7日頃)から
小雪(11月21日頃)
までに使う表現で、11月下旬は使いません。
でも「霜寒の候」は季節の様子を
表した言葉なので11月いっぱい使って
大丈夫なのです。
また、調べてみると、
三省堂のWEBディクショナリーでは
12月の時候の挨拶に
「霜寒の候」が紹介されているので
12月上旬くらいまでは
使ってもいいということなのでしょう。
最近は12月に入っても
まだ秋の終わりのような気候のことも
ありますから、
それに合わせてなんでしょうね^^
霜寒の候以外の11月の時候の挨拶は?

また、「霜寒の候」以外にも
11月に使える時候の挨拶の表現には
次のようなものがあります。
晩秋の候
暮秋の候
深秋の候
深冷の候
落葉の候
向寒の候
暮秋の候
深秋の候
深冷の候
落葉の候
向寒の候
ここで紹介したのは、いずれも
季節の様子を表現したものですので
11月いっぱい安心して使えますよ^^
スポンサードリンク
時候の挨拶の使い方
手紙の冒頭にはまず
「こんにちは」にあたる
「頭語」と言われる
拝啓
謹啓
から始まり、
次に「時候」の言葉を使います。
これが「霜寒の候」や「落葉の候」
などになります。
その次に相手への気遣い安否の
挨拶に続き
相手の繁栄を祝福する文から
自分の安否を添え、本文と続きます。
【例文】
拝啓 霜寒の候 皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になり、心よりお礼申し上げます。さて、(〜本文)
年末ご多忙の折ではございますが、お体にお気をつけて良き年をお迎え下さい。
敬具
伝える相手により様々ですが、
このように季節に合った
言葉を用いて
文章を書き添えます。
まとめ
最初は面倒に感じる時候の挨拶ですが、
知れば知るほど、そこには
素晴らしい自然の美しさや
言葉の豊かさ、
また、日本人の礼儀礼節を重んじる心と
文化の奥ゆかしさが込められています。
今、時代は情報化や
デジタル化が進み
豊かさに富んで数多くのツールに
囲まれ便利になってきました。
情報の多さに心の豊かさまでもが
埋もれてはしまわないように、
このような時候の挨拶を
使いこなせるようになっていきたいですね。
スポンサードリンク























